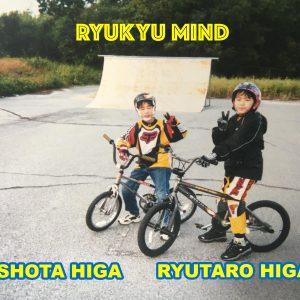ペグです。ペギーです。
遂に更新!続きを書くのに1年以上掛かってしまいました…
このシリーズの過去ブログはコチラからどうぞ。
もはや前回なにを書いていたか覚えていませんが、見返してみると今回は2016年からのお話みたいです。
BMXに限らず、この頃からシーンの主戦場はインスタグラムへと移っていきます。
インスタグラムで動画投稿が可能になったのは2013年で、最初は最大15秒。それが30秒、60秒と伸びていくにつれて、ライダーの表現の幅もどんどん広がっていきました。
(若い子は、インスタが元々“写真加工アプリ”だったの知ってるかな?)
それに伴い、フルレングスビデオやDVD、ウェブ映像は一気に減少。プロライダーでない限り、フルパートを見る機会はかなり珍しくなっていきます。自分も当時はビデオカメラでDVDやウェブ用に映像を撮り溜めていましたが、アウトプットに対する価値観は確実に変わっていきました。
映像が“手軽でインスタント”になったことは、ライディングの流行にも影響したと思います。
30〜60秒の短い尺の中で自分の世界観をどう見せるか。そして「どう投稿数を増やすか」を考えるライダーが増え始めた時期です。これはプロライダーでも同じでした。
プラットフォームがインスタントであれば、当然、内容であるライディングや編集もインスタントになっていきます。毎日毎日、時間をかけて撮影・編集し、ビッグトリックを狙うのは現実的ではないですからね。
身近に居たこともありましたが、当時のYumiの活動やライディングスタイルは本当に時代にフィットしていて、世界的に見ても抜群に光っていたと思います。とくに“スタイル”ですね。いい意味でインスタントなトリックでありつつ、しっかりと個性で差をつけていました。もちろんインスタントと言っても、裏側の努力や葛藤は見てきたつもりなので、中身まで簡単なものではなかったのは言うまでもありません。
ビデオパートを作る前にインスタグラムのクリップだけでスポンサーが付く。ライダーが“インフルエンサー”として機能し始めた時期でもあり、それを後押ししたのがSNSだったと思います。賛否はあるかもしれませんが、個人的にはライダーにとってもスポンサー側にとっても良い方向に働いたと感じています。
この頃から、乗り方やローカルの流行も“SNSの中”に存在するようになった気がします。
世界中の情報が一瞬で見られるようになったことで、「このエリアが強い」「この街のムーブが熱い」というより、「このスタイルがカッコいい」「この雰囲気が流行ってる」といった、場所に依存しないカルチャーの広がり方に変化していきました。
距離や国が離れていてもクルーとして成り立ったり、BMXブランドのプロチームも、それまではローカル色が強かったのが国境を越えた国際的なチーム構成へとシフトしたり。チームというより、ライダーがそれぞれの場所で独自に活動し、その個性が際立つようになったと思います。
昔は「FIT UK」(FITのイギリスチーム)のように、本家とは別にチームが存在していた例もありますが、そういった“地域性ありき”の形も徐々に薄れていきました。
そんな流れで、シーンは完全にSNS主体の時代に突入。
そして2025年の今に至るまで、この形は大きくは変わっていないように感じます。ただ、よく見ると小さな変化の兆しもあったりもします。
次回、いよいよ最終回(にしたい)。できれば年内に…。
現代編として、いま何が起きているのか、そして“次のトレンド”がどこへ向かうのかを書いてみたいと思います。(まだ落ち考えてない汗)